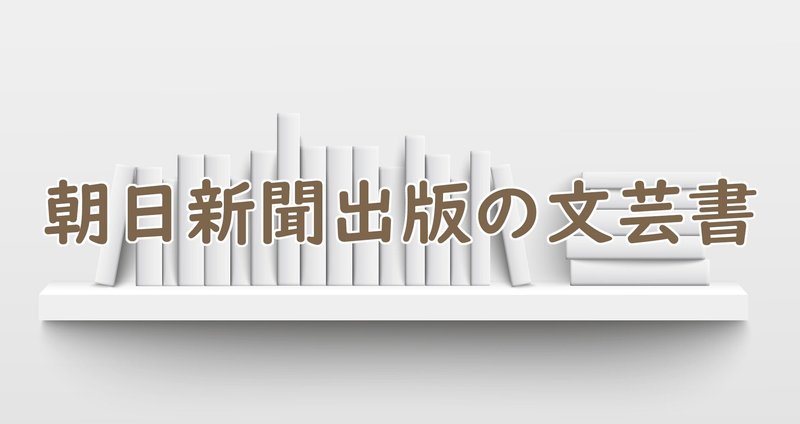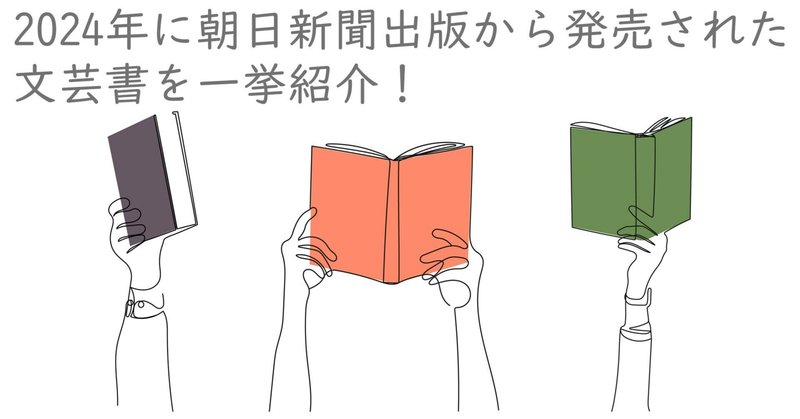記事一覧

田中慎弥さんがデビュー作から描いてきた「孤独な人間が最後に見出す、人生の『伴走者』」とは?/あわいゆきさんによる『死神』書評
かつて見捨ててしまった死神と、再び向き合うために――田中慎弥『死神』論〈死神〉ときいて脳裏に浮かぶイメージはなんだろう? フィクションのなかであらゆる姿かたちをとる死神は、多様すぎるがゆえに概念ばかりが朧げに共有され、実像がひとつに定まらない。中国古典文学を研究する増子和男さんは『日中怪異譚研究』(汲古書院、2020)で、一般的な〈死神〉概念を次のように定義している。 実際、脳裏に浮かんだ死神が、こうしたイメージと紐づくひとは多いはずだ。 だが、田中慎弥さんの『死神』に

多くの苦しむ女性に支持されたあのロングセラーが待望の文庫化!『母が重くてたまらない 墓守娘の嘆き』三宅香帆氏による解説を特別掲載!
信田さよ子の達成とは何だったのか。母娘問題やDVやアディクション(嗜癖)問題を扱う臨床心理士の第一人者であり、日本一本を精力的に出版している日本公認心理師協会の会長であり、さらにいまもカウンセラーとして臨床の場に立ち続けている。そういった達成は知られている。もちろん私も知っている。それでもなお、言いたい。信田さよ子の達成とは、日本の母娘問題に「夫」の姿を引っ張り出したことである。私はそう考えている。 本書は春秋社から2008年に刊行された。臨床心理士の信田さんが、カウン

冬季号は新連載2本がスタート、豪華時代小説競作、創作も掲載! 谷川俊太郎さん追悼文も。評論、対談も見どころ満載。〈「小説TRIPPER」2024年冬季号ラインナップ紹介〉
2024年12月18日発売の「小説TRIPPER」2024年冬季号のラインナップを紹介します。 ◆新連載伊東潤 「平清盛 日輪沈まず」 時は平安末期――。伊勢平氏の棟梁・忠盛は瀬戸内海の海賊退治で大功を挙げ、内昇殿を許される。一方、忠盛の嫡男・清盛は公家が支配する世に疑問を抱いていた。新たな政の仕組みを構築すべく、清盛は父・忠盛とともに日宗貿易に力を入れていく。武士の世を目指す改革者・清盛の真実に迫る歴史大河巨篇第1回。 木下昌輝 「我、室町の王なり」 時は室町

\これぞ伊坂幸太郎の集大成/「そうだ、こういうのが読みたかったんだ、と思った。」/大矢博子さんによる『ペッパーズ・ゴースト』文庫解説を特別公開!
※解説は本作のストーリー展開に少々触れている箇所がございます。ご注意下さい。 2020年に新型コロナウィルスが世界を襲ってからというもの、最初の半年は混乱の中に放り込まれ、次の1年は次々更新される情報と新しい生活様式になんとかついていこうと頑張り、そして2021年の秋には、私たちはすっかり疲れ果てていた。 そんな時に刊行されたのが本書『ペッパーズ・ゴースト』である。 飛沫感染で未来が見える超能力……? それまでの人生でほとんど使ったことがなかった「飛沫感染」と