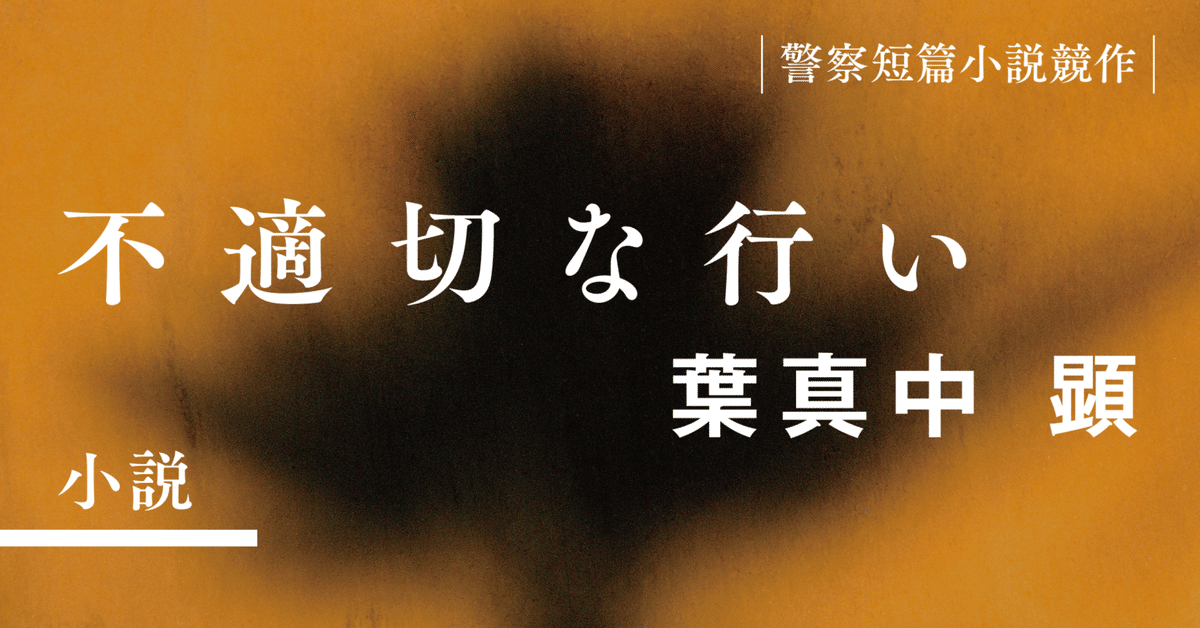
不適切な行い
葉真中 顕
1
雨戸を開けると、空には雲ひとつなかった。先週、地面を湿らす程度の雨が降ったきり、ずっと晴天が続いている。今年は例年にない空梅雨のようだ。
朝食を済ませて、さっと歯を磨き、パジャマからスーツに着替え、身支度を調える。居間の奥の仏壇の水を替え、線香を一本取り出す。ライターで線香を焚き、仏壇の香炉に立てる。りんを鳴らし、手を合わせる。
今日もしっかり、務めを果たしてくるからな──息子、正義の位牌に誓うところまでが、私の朝の日課。最近の言葉で言うならルーティーンだ。
そのさなか、スーツのポケットの中でスマートフォンが振動した。取り出して画面を見る。最近、老眼が進んできて裸眼では文字がぼやけるが、辛うじて〈屯倉署 刑事課〉と表示されているのがわかった。警電からの着信だ。
画面をタップして、電話に出た。
〈佐原係長、ご苦労様です。み、水越です〉
昨夜の当直番だった若手の刑事である。
「どうした?」
あと三十分もすれば署で顔を合わせる私に、わざわざ電話してくることから、なんらかの緊急事態だということは察せられた。水越の声色もいつになく硬い。重大事案だろうか。
〈死体が出たと、通報がありました〉
案の定だった。
〈場所は千間沢。女性。埋められていたようです。あ、えっと、地域課員が急行しています。自分も、連絡を回し次第、向かいます〉
普段は冷静な水越も珍しく慌てていることが伝わってくる。
千間沢は、ここX県屯倉市の北部に位置する山地だ。そんな場所に埋められていたということは、十中八九、殺人だ。
「わかった。俺も直行する」
〈お願いします。すぐに位置情報送りますので〉
「頼んだ」
電話が切れた数秒後、またスマートフォンが振動し、現場の位置情報が送られてきた。便利なものだと思う。備品として一人一台のパソコンが支給されたのは、もう十年以上前だったか。今や捜査にIT機器を使うのは当たり前だ。
そのことに限らず、私が任官した三十年前と比べると、警察組織はずいぶんといろいろなことが変わった。私が新人の頃はまだ上司や先輩の鉄拳制裁も珍しくなかったが、今、そんなことをすれば立派なパワハラだ。
一方で変わらないものもある。たとえばそれは治安を守る公僕としての責任だ。どれだけITが発達しても、結局は「人間」の仕事であるという部分も変わらないだろう。
気づけば私もベテランと呼ばれる歳になった。今は屯倉署刑事課の係長として「刑事一係」を率いている。古い時代の悪弊は引き継がず、この三十年で培った経験を部下たちに伝え、鍛えてゆくのが、今の私の役目だと思っている。
もちろん、自ら現場に出て、だ。
「どうやら事件みたいだ。行ってくるよ」
私は今度は声に出して正義の位牌に告げて、立ち上がった。
2
惨い。ひと目、そう思った。
千間沢の西の麓。山道から脇にそれた森の中。クヌギの木がまばらに生える空間に、その死体は横たわっていた。着衣をなにも身につけず、全身が土で汚れている。髪の長さと体型で女性だとわかる。その右の上腕から前腕にかけて、左の二の腕、乳房の片方、腹、両の太腿、そして顔の頬の部分の肉が削がれており、骨が露出していた。眼窩に収まっていたはずのふたつの眼球もなくなっている。
なんとも、惨い。
私が到着したときには、すでに先着した捜査員らによる鑑識作業が始まっていた。連絡をくれた水越も、それに加わっている。県警本部にも連絡済みで、ほどなく検視官が臨場し、この場で検視を行う手はずだという。
「第一発見者は、近隣に住む老夫婦です。近隣と言っても住まいは一キロ近く離れてますが、今朝の五時過ぎ、ウォーキングがてら、山菜採りに訪れたところ、死体を見つけたそうです。今、車両でより詳しく話を訊いています」
鑑識作業を仕切っている鑑識係の大貫が説明してくれた。
この森の反対、千間沢の東側にハイキングコースが整備されて以来、こちらには滅多に人は訪れないらしい。発見者の老夫婦も、普段人が行かないからこそ、山菜が採れるのではないかと、思いつきで訪れたようだ。
「そこに埋まっていたんでしょうね」
大貫は死体の傍らの地面を指さした。そこには雑に掘り返したような大きな穴があった。
「タヌキの仕業か」
「たぶん。まあアナグマかもしれませんが。動物で間違いないでしょう。匂いで餌が埋まっていることに気づいて、引っ張り出して、食ったと思われます」
死体の肉が削げているのは、比較的柔らかい部分だ。
タヌキやアナグマ、あるいは野犬などの野生動物は、雑食で人の肉を食う上に、高い穴掘能力を持っている。一メートル以上の深さに埋めた死体でも掘り返してしまうことがあるという。そうした話を聞いたことはあったが、実際に目の当りにするのは初めてだった。
「死後の経過時間と、死因は?」
大貫は苦笑してかぶりを振った。
「わかりません。掘り返されてからさほど時間は経ってないでしょうが、どのくらい地中にいたのか。地中では死体の腐敗進行速度が遅くなるのは間違いないですが、条件によりますからね。まあ、検視で詳しく死体を調べれば、経過時間はある程度しぼれると思います。ただ、死因の特定は不可能でしょう」
「そうか。でも、いずれにせよ、死体遺棄は確定だな」
「ええ。それは間違いないでしょう。動物が死体を掘り返すことはあっても、埋めることはないですから。埋めたのは人です。十中八九、殺人と思われます」
大貫は一報を受けたときに私が思ったのと同じことを口にした。
長閑と言われるこの屯倉市では大事件だ。マスコミの注目を集めるのは間違いないし、署には捜査本部が設置され、大々的な捜査が行われるだろう。
今、この時点でこの死体を埋めた犯人にとっては、不運が重なっていると言える。
ひとつは、死体が野生動物に掘り返されたこと。そしてもうひとつは、それから大して時間が経過しないうちに、たまたま訪れた人に発見されたことだ。死体が発見されなければ、この女性は行方不明者の一人に数えられていた可能性が高い。
逆に警察と、きっと無念の死を迎えただろうこの女性にとっては、死体が発見されたことは不幸中の幸いだ。死んでしまった者に幸も不幸もないかもしれないが、せめて犯人に酬いを受けさせたい。
そのためには、まずは身元だ。この女性がどこの誰かを明かすことが、捜査の一丁目一番地になる。
犯人は死体を全裸にして埋めた。万が一、死体が発見されても身元をわかりにくくするため、と考えるべきだろう。衣類や所持品は別で処分したに違いない。犯人の周到さが窺える。
私は改めて、その惨い死体を見つめた。
残っている部分の肌の感じや、髪の毛、額、鼻筋などからして、老人ではないのは確かだ。子どもでもない。断定はできないが、四十より下の若い女性ではないだろうか。
顔立ちはほとんど原形を留めていないが、輪郭はある程度わかる。
──正義。
不意に息子のことを思い出した。あいつも人里離れた山地で命を落とした。
もっとも正義は殺されたわけではない。事故だった。一昨年の夏、ここ千間沢ではない県内の別の山で登山中、岩場から滑落してしまったのだ。まだ大学生になったばかりの十九歳だった。
私はそれまでに刑事の立場で、何人かの我が子を亡くした親に会ったことがあった。彼らの哀しみや無念を理解していたつもりだったが、逆縁が我がこととして降りかかってきたとき、それらは実際に経験しないと本当にはわからないものなのだと思い知った。
妻は心労が重なったこともあり、今でも実家で療養している。私だって本当に立ち直れているのか、わからない。この胸の奥には、重い哀しみが鎮座している。
しかし、私までもが塞ぎ込んでしまえば、きっと天国のあの子を哀しませることになる。
──俺、大学出たら任官試験、受けます。父さんみたいな立派な警察官になりたいんだ。
大学に合格した記念に家族で外食したとき、正義は、そう言った。言ってくれた。法学部を選んだのは法律の知識を学ぶためで、趣味の登山は体力づくりを兼ねてのことだった。
あいつが警察官になりたいと言ったのはあのときが初めてではなかった。小学生の頃から、作文に「将来の夢は警察官」と書いていた。親の仕事に漠然と憧れる子どもは少なくないそうだが、正義は思春期を過ぎてもその気持ちを持ち続けていた。私は何度か、テレビドラマのように格好いい仕事じゃないぞと、現実の警察官の大変さを話して聞かせたが、むしろその度に意欲を高めたようだった。
私はあいつが幼い頃から、道理に合わないことはするな、約束は守れと厳しく躾けてきた。それを煙たがる様子もなく、この背中を追おうとしてくれていた。順調に行けば、私が定年する少し前に正義が任官し制服に袖を通すことになるはずだった。
もうそれは叶わないが、職責をまっとうすることこそが、あの子に報いることなのだと思う。毎朝、位牌に手を合わせ誓うあの日課は、哀しみに飲み込まれず気持ちを奮い立たせるためでもある。
この女性にも父親はいたはずだ。もちろん母親も。彼らは、娘がこのような目に遭っていることを知らないだろう。あまりに不憫だ。
必ず、この女性の身元を明かし、犯人を挙げてみせる。
と、そのとき、ぷうんと、アルコールの臭いが漂ってきた。それと重なるような、間延びした声。
「あらら、こら、悲惨なことになってんなぁ」
振り向かなくても誰かわかった。
我が刑事一係の問題児。いや、問題爺と言うべきか。ベテラン刑事の柿沼だ。
「飲んでるんですか?」
私が一瞥すると、柿沼は悪びれずに、にへらっと笑って、そのごま塩頭を掻いた。
「いやあ。今日は非番だもんで。向かい酒としゃれ込んでたんですわ」
こうした重大事件が起きた際は、非番の者でも呼び出される。が、この男には声をかけなくてもよかったのにと、正直、思う。
「それはお休み中、ご苦労様でした」
「いやあ、暢気に休んでられんですよ」
皮肉を言ったつもりなのだが、柿沼には通じなかったようだ。
そんなこと言うなら、せめて酒は抜いてこいよと思う。
手前味噌かもしれないが、私は刑事一係の部下たちをどこに出しても恥ずかしくない刑事に鍛え上げている自負がある。しかし、この柿沼だけは別だ。
柿沼の階級は巡査部長、役職は主任。刑事一係では私に次ぐナンバーツーの立場だ。が、年齢は私より八つ上で、しかも私が新人時代、最初に配属になった署の先輩だった人物である。どういう天の配剤なのか、柿沼はあの頃からほとんど出世もせず、今は屯倉署で私の部下になっている。
正直、やりにくい。部下ではあっても一応、先輩なので話しかけるときは敬語を使うし、他の部下のように「指導」するわけにもいかない。
柿沼が、模範となるような刑事ならそれでも問題はないのだが、残念ながらそうではない。昔は、少し緩いところのある先輩だと思っていたが、長い時間をかけてその緩さに磨きがかかったようだ。朝礼への遅刻や、申し送りの不徹底など、後輩の見本にならない不適切な行いを日常的に繰り返す。捜査でペアを組ませた刑事から、やたらと休憩を取りサボりたがると報告を受けたこともあった。
これでは他の者に示しがつかないと思い「いい加減にしてください!」と怒鳴りつけてやったこともあるが、「すまん、すまん」とへらへら受け流すばかり。さすがに頭に血が上り「その態度はなんですか」と襟首を掴めば、「暴力反対。パワハラじゃねえですか」などと宣う。
処置なしだ。
幸いと言っていいのか、柿沼は今年で五十九歳。来年には定年を迎える。それまでは、反面教師として、利用するしかないと思っている。今回の捜査では、役に立たなくていいから、せめて足は引っ張ってくれるなと祈るほかない。
その柿沼は、身をかがめ死体を覗き込むと、「んー?」と、首をひねった。
「どうかしましたか?」
尋ねると、柿沼はこちらに顔を向け、「あー、やっぱ、なんでもねえです」と、大げさに肩をすくめた。
やっぱって、なんだよ? なんなんだ、この人は!
柿沼が妙に思わせぶりな態度を取ることは珍しくないので、私はただ憤りを覚えるだけだった。しかし、おそらく彼はこのとき、隠し事をしていたのだ。
3
死体発見の数時間後、県警捜査一課が応援に乗り込んできて、屯倉署には捜査本部が設置される運びとなった。
千間沢死体遺棄事件──署の大会議室の入口に、そんな事件名を書いた紙が貼られ、中にはホワイトボードや、電話機などの備品が運び込まれた。
捜査本部では、どうしても主導権は県警が握り、我々所轄署の刑事は、そのサポートをすることになる。全体の指揮をとる「捜査主任官」を務めるのも県警捜査一課の管理官だ。
しかし現場で遠慮する必要も気後れする必要もない。むしろ連中をリードするつもりで捜査にあたれ──私はそう部下たちに発破をかけた。
精鋭部隊とされる県警捜査一課は、基本的に一本釣り、すなわち見込みのありそうな所轄の刑事をスカウトする形で捜査員を補充している。所轄の刑事にとって捜査本部に加わることは、アピールのチャンスでもあるのだ。私の部下たちなら、今回の捜査を通じて、捜査一課から誘いを受ける者も出てくるはずだと、密かに思っている。
検視とそののちに行われた科学鑑定の結果が出たのは捜査三日目のことだった。
死体発見現場で大貫が言っていたように死因は特定できなかったが、死亡時期については概ね三ヶ月前だろうと推定された。
その翌々日、捜査五日目には、死体──被害者──の身元が判明した。
県の歯科医師会を通じ照会を依頼したところ、被害者の歯形と歯の治療痕から、市内の歯科医院で治療歴のある女性だと特定できたのだ。その日の夜の捜査会議で、全捜査員に情報が共有された。私が被害者の身元を知ったのもそのときだった。
「被害者の名前は、西郷優花。西郷隆盛の西郷に、優しいに、花で、西郷優花です。歳は二十四歳──」
会議室の前方で担当の捜査一課の刑事が報告をした。歯科医院の受診記録によれば、西郷優花の住まいは市の南側の住宅街にある『カーサ屯倉南』というマンションの一室。受診時に提示した保険証が、国民健康保険のものだったことから、企業に勤める正社員ではなかった可能性が高い。そのほか、詳しい素性は現時点では不明。急ぎ、数名の捜査員と鑑識班がそのマンションに向かっているという。
続いて管理官が、今後は西郷優花の住まいを捜索するとともに、職業や交友関係など、身辺を洗ってゆくことを確認した。被害者の身元が判明したことは大きな前進と言えるだろう。
が、私は報告を聞きながら奇妙な感覚に囚われていた。
西郷優花という名前を知っている気がしたのだ。知り合いに西郷という姓の者はいない。自分が関わった事件の関係者にもいなかったはずだ。では、なんだ? いわゆるデジャビュというやつだろうか。それにしては、はっきりとしたひっかかりがある気がする。
その正体がわかったのは、会議が終わった直後、部下が二人、私の元にやってきたときだ。
水越と、刑事一係の紅一点、女性刑事の宮原だった。
二人とも、表情を強張らせていた。
「あの、係長、被害者の、西郷優花という女性なんですが、以前、相談に来て……」
水越が神妙な顔つきで口を開いたとき、思い当たった。
「もしかして、脅迫で被害届を出した女性か」
「はい」と、水越が答え、隣で宮原も頷いた。
たしか、暴力的な恋人と別れようとしたら脅迫を受けたと相談に来た女性が、一度は被害届を出したものの、すぐに取り下げたため捜査には至らなかった事案だ。水越と宮原が担当し、私は調書と口頭での報告を受けた。その女性の名前が、西郷優花だった。調書に書かれた字面をはっきりと思い出した。
「同一人物なのか?」
念のため尋ねると、宮原が「はい。間違いないです」と答えた。
「脅迫の事実は、あったのか?」
二人は顔を気まずそうに見合わせ、宮原が口を開いた。
「本当に、あったんだと思います。西郷さんが最初に相談に来たとき、対応したのは私でした。恋人に別れを切り出したら、首を絞められて、殺すと脅されたって話していました。実際、首のところに痣もできていて、私はもうその時点で被害届を出してはどうかと提案したんですが……」
宮原は一度言葉を切り、眉間に皺を寄せた。
「そのとき署にいた柿沼さんが割り込んできたんです。こんなことで被害届出されても受理するわけにはいかないって」
「突っぱねたのか」
「はい。証拠がないだろうって。西郷さんは、痣ができるくらい強く首を絞められて、本当に殺されるかと思ったって、訴えたんですが、診断書がなければ証拠にならないって」
たしかに、証拠のない訴えを真に受けて事件化すれば、冤罪を生みかねない。この世には他人を嵌めるために虚偽の被害を訴える者もいる。だが、柿沼のことだから、そうした心配をしたわけではなく、単純に仕事を増やしたくないと思ったのだろう。
宮原もそう思っているようで、しかめ面のまま続けた。
「あの人、面倒だったんだと思います。本来だったら、被害届は全部受理すべきなのに」
警察活動の規則をまとめた「犯罪捜査規範」では、そう定められている。現実の実務では、明らかに虚偽だったり、刑事事件にはならないトラブルを元にした被害届は受理しないこともあるが、この西郷優花のケースは、宮原の言う通り、受理すべきだろう。
「でも、結局は受理したんだよな」
「はい。その次の週に西郷さんもう一度来て、今度は証拠もあるって。SDメモリーカードを持ってきたんです。そこにはっきり男の声で『ぶっ殺すぞ!』って声が録音されていました。西郷さん、わざと別れ話を切り出して、恋人が怒る様子をスマートフォンで録音したそうです。そのとき、ちょうど柿沼さんがいなくて、水越さんと」
宮原が隣の水越に水を向けた。水越は頷き、続きを引き取るように口を開いた。
「宮原から事情を聞いて、柿沼さんがいないうちに受理してしまおうって、自分たちの判断で受理することにしたんです」
なるほど。その音声データは脅迫罪の証拠になりえる。西郷優花は危険を冒してまで証拠を用意したのか。そうした詳細は調書ではわからなかった。しかし、だったら、なぜ。
「西郷優花は、そうして証拠まで用意して被害届を出したのに、すぐに取り下げたんだよな?」
「そうなんです」引き続き、水越が答えた。「被害届を出して、確か二日後の深夜、西郷さんが署にやってきて、たまたま自分が当直で対応しました。改めて恋人と話し合ったら、向こうの態度が変わって円満に別れることができたんで、被害届をなしにしたいと」
「それで、取り下げに応じたのか?」
「結果的には……」
私は思わず顔をしかめた。
「おまえ、その恋人から被害届を取り下げるように脅されたとは考えなかったのか」
「それは何度も確認しました。西郷さんは、恋人は被害届のことはまだなにも知らない、せっかく円満に別れられたのに、警察沙汰になったら逆恨みされる。逮捕して一生刑務所に入れられるなら、そうして欲しいけど、それができないなら、なにもしないで欲しいと……」
たしかに円満に別れられているのであれば、警察が介入することが藪蛇になりかねない。
「その言い分はわからんじゃないが、その場で、はいそうですかと、応じるもんじゃないだろ」
「もちろん、自分の独断ではなく、電話で判断を仰ぎました。柿沼さんに、なんですけど」
また、あの男の名前が出てきた。
「じゃあ、判断したのは、柿沼……さんか」
一瞬、呼び捨てにしかけ、一拍遅れて「さん」をつけた。
「はい。柿沼さんは、そもそもただの痴話げんかだったんだろうし、警察がしゃしゃり出た方が、ややこしいことになる、取り下げに応じろ、と」
そういうことか。柿沼が背後でうろちょろしていたわけだ。
「あれ、三月だったよな」
「そうなんです。ちょうど三ヶ月前、でした」
答えた宮原の声は震えていた。
西郷優花の死亡時期と重なる。
その恋人とやらが、殺して埋めた──そんな筋が容易に想像できる。やはり脅して被害届を取り下げさせていたのか。あるいは本当に円満に別れたが、なにかきっかけがあって逆恨みされたのか。
いずれにせよだ。もし恋人が犯人なら、トラブルを把握しておきながら、事件を防げなかったことになる。
「まずいぞ」
私自身、被害届が出されたことと、それがすぐに取り下げられたことは、調書で知っていた。妙な話だとは思ったものの、特に追及はしなかった。甘かった。だが、今更悔やんでも詮無い。今できる最善を尽くさなければ。
そのとき不意に、ひとつ、気づいたことがあった。
「おまえらは、さっき会議で名前が出て被害者が西郷優花だと気づいたんだな。現場ではわからなかったか?」
「あの、私は、現着が送れて、死体を目にしなかったので」と、宮原。
「自分は見ましたが、顔立ちもわからなくなってましたから。言われて、思い返せば、そうだったのかと思いますが」と、水越。
だが、現場でも気づいたやつがいたんだ。柿沼だ。
やつが死体の顔を覗き込んでいた理由がわかった。
なにが、なんでもねえです、だ!
辺りを見回すと、私たちがなにやら深刻そうに話し込んでいるからか、会議室に残っている県警の刑事たちが、ちらちらこちらを窺っている。
私は、大きく息を吐いた。
「とにかく、上に報告しよう。宮原、刑事部屋からそのときの調書とってきてくれ」
「はい!」
宮原は、駆け足で会議室を出ていった。
「俺たちは先に説明しよう」
水越を促し、前方に設置された幹部席にいる管理官の元へ向かう。
これは屯倉署にとっては不祥事になるかもしれない。しかし、隠すことはできないし、隠すわけにはいかない。相談を受けたときの調書には多くの情報が含まれるだろうし、西郷優花の恋人が有力な被疑者なのは間違いないのだから。
4
「いやあ、こりゃあどうも面倒なことになりましたなあ」
柿沼にはまったく悪びれる様子がなかった。
「柿沼さん、あんた、どうして西郷優花が最初に相談しに来たとき、横やり入れたんですか」
「あんときは証拠がありませんでしたからな。我々が冤罪をつくり出したらまずいでしょう」
署の中央階段、屋上手前の踊り場。普段ほとんど人が訪れることはなく、湿った空気が揺蕩っているこの空間で、私は柿沼と向き合っていた。
捜査開始からちょうど一週間。今日は朝から空に梅雨らしい灰色の雲が広がり、雨を降らせている。
三月に西郷優花が被害届を出したときの調書と、応対した水越と宮原の弁により、彼女の素性ははっきりとした。
西郷優花は二年ほど前から、屯倉駅駅前の繁華街にある『ジュピター』というクラブでホステスとして働いていた。未婚で歯科の診療記録にもあった『カーサ屯倉南』で独り暮らし。昨年の秋頃から、客だった尾崎洋司という男と付き合うようになったという。
この尾崎洋司が件の脅迫をしていたという恋人だ。現在二十八歳で、父親が経営する『尾崎殖産』という不動産会社に籍を置いている。地元の不良の間では有名な存在で、未成年の頃から複数回の補導歴があり、成人後は傷害で二度も逮捕されている。しかしその二度とも父親が金を積んで被害者と示談し、不起訴処分となっている。父親は市内では名士ということになっているが、息子に甘いことでも有名らしい。
画に描いたようなどら息子である尾崎洋司は、気にくわない相手のことは父親の人脈を駆使してでも徹底的に追い込むところがあり、恐れられている反面、友人や後輩にはいつも気前よく奢っており、不良の間では人望があるようだ。
西郷優花も付き合う前から尾崎洋司の名前は聞いたことがあったらしい。そんな「有名人」が、足繁く店に通い、情熱的に自分のことを口説いてきたことでその気になり、付き合うことになったという。初めのうちは頼もしいと思っていたが、次第にその粗暴な性格や素行の悪さに付いていけなくなった。大怪我をするような暴力は振るわれていないが、大声で罵倒されたり、頬を張られたりといったDVもあったようだ。
今年に入ってから西郷優花は何度か別れ話をしてみたが、応じてもらえず、脅迫を受けるようになった。このことは勤め先の『ジュピター』の同僚にもこぼしていたという。
そして西郷優花は、警察を頼ることを決意した。
最初に相談に来たのが、三月二日。水越たちが述べたように、このときは柿沼の横やりが入り被害届を出せなかったが、その六日後、三月八日、西郷優花は証拠となるSDメモリーカードを持参してきて、被害届を出し、受理された。しかし、三月十日の深夜、それを取り下げた。
西郷優花が最後に『ジュピター』に出勤したのは三月九日。被害届を取り下げる前日だ。そしてこのとき同僚の女性が、西郷優花が仕事が終わったあと店の外で、誰かとスマートフォンで話しているのを見かけている。相手も話の詳しい内容も不明だが、西郷優花が「そんなこと言われても困る」と言っているのを聞いていた。そして西郷優花は店に来なくなった。マネージャーが何度か電話してみたが、つながらなかったそうだ。
死体発見後の聴取によると、西郷優花が尾崎洋司と揉めていることは『ジュピター』の関係者はみな知っており、なにかトラブルがあったのかと思ってはいたが、巻き込まれることを恐れ、誰も確認しようとはしなかったようだ。「水商売の世界では急にキャストが無断欠勤してそのまま退店することは珍しくないんです。事情もそれぞれですから、深く追求しませんでした。けれど、まさか、死んでたなんて夢にも思いませんでした」とは『ジュピター』のマネージャーの弁。同僚だったキャストたちもみな、似たり寄ったりの、言い訳めいたことを言っている。
鑑識が西郷優花の住まいである『カーサ屯倉南』の部屋を詳しく調べたところ、壁の巾木の隙間に少量の血液が付着しているのが発見され、DNA型から西郷優花のものだと断定された。
こうした情報から上層部は、尾崎洋司を最有力の被疑者とした。
プライドが高い尾崎洋司は、西郷優花が被害届を出したことを知り強い憤りを覚え、殺意を抱いた。態度を改め円満に別れる振りをし、西郷優花に被害届を取り下げさせ、その上で彼女の自宅で殺害。死体を千間沢に埋めた──といった筋読みだ。
私もそれが一番可能性が高いと思う。しかし証拠は今のところ何もない。
西郷優花が殺害されたのは、おそらく被害届を取り下げた直後なのだが、いつかはわかっていない。ゆえにアリバイから容疑を絞り込むこともできない。
今のところ参考人という形で、尾崎洋司から何度か話を訊いているが、彼は「俺も急に優花と連絡が取れなくなって心配していた」などと述べている。今年に入ってから別れ話を持ちかけられたことは認めたが、そのことで西郷優花を脅してなどいないし、彼女が警察に被害届を出したことも知らなかった、と証言している。
自白を取れれば話は早いが、聴取を担当した捜査一課の刑事によれば、尾崎洋司は、悪い意味で警察馴れしており簡単に落ちる相手ではなさそうだということだ。
西郷優花が被害届を出したときに提出したSDメモリーカードがあれば、決定的な証拠とは言えなくても、突破口になりえる。少なくとも脅迫の容疑での逮捕は可能だろう。被害届の取り下げ時に西郷優花に返却したそうだが、彼女の部屋からは見つかっていない。スマートフォンや携帯電話の類もだ。自らへの疑いをかわすため、殺害時に尾崎洋司が奪って処分した可能性がある。
捜査本部の誰もが解決まであと一歩のところまで来ている感触を得ているが、その手前に壁があるような状況だ。
加えて我々屯倉署にとって問題なのは、三月の時点で、西郷優花に被害届を取り下げさせず、捜査を始めていれば、今回の事件を未然に防げた可能性はきわめて高いということだ。
私は柿沼に問いを重ねる。
「じゃあ、取り下げの方はどうです。三月十日の夜、水越から判断を仰ぐ電話があったんですよね」
「ええ。話を聞いてね、そりゃまあ円満に別れられるなら、茶々入れることもねえだろうと、応じていいんじゃねえかと思いましてね」
「深夜ですよね。せめて一日待つとか、慎重に判断しようと思わなかったんですか」
「今思えばね、その方がよかったような気もしますが……。あんときは、善は急げって思ったんですよ」
やはり柿沼は悪びれもしない。
何言ってやがる、あんたは仕事を減らしたかっただけだろう。次の日になって私の耳に入れば、取り下げに反対されると見越してのことだろう。いや、そうだったら、まだいい。
「柿沼さん、あんた、まさか噛んでないよな」
私は柿沼をまっすぐに見て尋ねた。
「は?」
「正直に言ってくれ。あんた、西郷優花が相談に来たこと、それから被害届を出したこと、尾崎に漏らしてないか。水越に被害届を取り下げるよう指示したのも、尾崎のためじゃないか」
「おいおい、そりゃ、なんぼなんでもだ。そんなことするわけねえだろ」
柿沼の顔から、へらへらした笑いが消えた。さすがに怒ったか。それとも、怒った振りをしているのか。
「柿沼さん、『尾崎殖産』の近所に住んでいるよな」
調書を読んでいて気づいたことだった。尾崎洋司の勤め先であり、実家でもある『尾崎殖産』は、市内の柿沼の住まいのある町にあった。
柿沼はわかりやすく顔をしかめた。
「それがなんだってんすか。管轄内に住んでんだから、そういうこともあるでしょうよ」
「まあな。それで『尾崎殖産』の社長、尾崎洋司の父親は、あんたの町の町内会長でもあるっていうじゃないか。ひょっとして面識があるか」
「そりゃ……。尾崎さんは顔の広い人だし、会えば挨拶くらいするよ」
「尾崎洋司のことも前から知っていたか?」
「有名な不良息子だからね。でも、俺が一方的に名前を知ってただけで、話をしたこともないですよ」
「だったら、最初に西郷優花が相談しに来たときも、尾崎洋司の名前が出た時点で、『尾崎殖産』のどら息子だって気づいたわけだな」
柿沼はふて腐れたように舌打ちした。
「いちいち言うようなことじゃねえでしょ。佐原さん、あんた俺が、尾崎さんが知り合いだから、忖度したとでも言いたいのか」
「知り合いだからじゃなくて、『尾崎殖産』に恩を売りたいからだ。定年後の身の振り方を考えてな」
柿沼のような警察官にとって、定年後の再就職先の確保は切実な問題だ。『尾崎殖産』のような市内の有力企業に貸しをつくることは大きい。
「そんなわけ、ねえでしょ」
柿沼は鼻を鳴らした。
「柿沼さん、上層部はこの件、重く見てるぞ。あんただけじゃなくて、俺や水越たちも、いったん、捜査から外されることになったんだ」
先ほど管理官から告げられた。捜査幹部たちは、事件が解決したあと責任追及されることを恐れているのだろう。
「へえ、そりゃ本当に面倒なことになっちまってますな」
柿沼は口角を上げた。その態度に憤りを覚えた。
「ふざけるな!」
私は柿沼の襟首を掴み、身体を壁に押しつけた。
「あんた、もし、尾崎のために動いたなら、正直に言え!」
あとから発覚するくらいなら、こちらから報告した方がましだ。
「ちょっと、勘弁してくれよ。んなこと、してねえって。単に仕事を増やしたくなかっただけだよ。わかんだろ」
柿沼は私の身体を押し返しながら、言った。
「仮にそうだとしても、問題だ!」
「悪かったよ。俺の判断が間違っていた。管理官にもそう言うよ。それでいいだろ。佐原さん、手ぇ離せよ。これパワハラだぜ」
柿沼はそんなことを宣い、私の手を振り払った。
5
俺の判断が間違っていた──そう柿沼が認めたところで、あいつ一人の問題では済まないだろう。屯倉署全体の不祥事ということになる。この先のことを思うと胃が痛い。
刑事部屋に戻ると水越と宮原の姿があった。私は二人に「ちょっといいか」と声をかけて、空いている会議室へ促した。
「──そういうわけで、捜査から外されることになった」
私が告げると、二人は顔を見合わせ、ほぼ同時に「申し訳ありません」と頭を下げた。
「顔を上げろ。悪いのは柿沼だ。おまえらは、とばっちりを食ったようなもんだろ」
今度は柿沼のことを呼び捨てにした。
水越も宮原も県警捜査一課への配属を希望していた。今回の事件で、捜査本部に加われたことはまさしくチャンスだった。二人とも私にとっては子どものような存在で、手塩にかけて育て、鍛えてきた。特に水越は捜査一課でも十分通用するだけの実力を備えていると思う。しかし、こんなことがあったのでは、引き抜かれることは当面ないだろう。
柿沼の不適切な行いのせいで、将来のある若手がわりを食うのは、忍びない。
でも、と宮原が口を開いた。
「柿沼さんがああいう人なのは、わかっていたことです。そもそも最初に西郷さんが相談に来たときから、私があの人を関わらせなければ、こんなことには、ならなかったかもしれません」
「まあな。たしかにそうかもしれん。だが、たらればを言っても詮無いだろ」
私は息をついて、水越に視線を向けた。
「水越、おまえもな。柿沼なんかに判断を仰がなければな」
あれはある意味決定的だった。怠け癖のある柿沼に判断を仰げば、被害届の取り下げに応じろと言うことは十分予想できたはずだ。もう取り返しがつかないが、残念だという思いで言ったのだが、水越は「本当に、申し訳ないです」とまた謝った。見ると、顔色も悪い。自分を許せないのかもしれない。
「終わったことは仕方ない。お前たちはまだ若いんだ。同じことを繰り返さないように、今後に活かせ」
「はい」
「はい……」
二人は返事をした。水越は顔色が悪いままだ。よく見ると口元が震えている。
「おい、水越、そんなに落ち込むな」
水越は顔を上げると「はい」と返事をした。その声にも覇気がなく感じる。
単に落ち込んでいるだけではなく、体調でも悪いのだろうか。
死体が発見されたと電話で連絡をくれたとき、水越の声が妙に上ずっていたことを思い出した。あのときは、大きな事件に緊張しているのかと思ったが、ずっとどこか具合が悪かったんじゃないのか。
そんな思いを巡らせているうちに、ふっと思い出したことがあった。
「ああ、そう言えば、水越、おまえ──」
私は特に何か確信や疑念があったわけではなく、ただ思い浮かんだ疑問を口にしただけだった。
「──どうして、死体が埋められていたってわかったんだ?」
あのときの電話で、水越はたしかに「埋められていたようです」と言っていた。しかし、発見時、死体は埋まっていなかった。野生動物に掘り返された上に一部白骨化していたのだ。近くに掘り返した跡はあったが、通報者が「死体が埋まっています」と通報したとは思えない。
あの電話は、署からかかってきたから、水越が現場を直接見て、そう判断したわけでもない。先に現着した捜査員から連絡があり、情報を持っていたのだろうか。
そんなふうに考えていた。
「え、あ、それは……」
水越は目に見えて動揺していた。いつの間にか、はあはあと、はっきり聞こえるほど荒く息をしていた。
「おい、水越、どうした?」
「水越さん、大丈夫?」
彼の隣に座っている宮原も声をかけた。
「ごめん、なさい」
水越は絞り出すような声で謝罪の言葉を吐き出した。そして、一度椅子から立ち上がると、その場で土下座をはじめた。その両目からは涙を溢れさせていた。
「ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、……ごめんなさい! 自分が、やりました」
おそらく水越は、ずっと罪悪感に苛まれていたのだろう。隠蔽工作がいつかばれるのではないかという恐怖に怯えていたのかもしれない。もともと真面目な男だ。自ら犯した罪を隠し、すべてなかったことにして、生きてゆくことなどできなかったのだろう。
図らずも私が、彼の犯行を間接的に裏付けるような質問をしたとき、良心と保身の間でぎりぎり張り詰めていた糸が、切れたのだろう。
しかしこのときの私は、その突然の行動に驚くばかりで、この期に及んでまだ、水越が何をやったと言っているのか理解できていなかった。
水越本人が口にするまで。
「自分が、西郷優花さんを殺して、千間沢に埋めたんです!」
6
「取り調べを行っている捜査員によれば、動機は、紛失、だそうです」
署の会議室。先週、水越が座っていたのと同じ場所で、その菰田肇という男は私と向かい合っている。彼は話すときほとんど表情が変わらない。顔立ちは若いのに髪は半分以上白髪だ。何歳くらいなのだろう。私より年上なのか下なのかもわからなかった。
「紛失、ですか?」
私は訊き返した。どういうことだ?
「はい。水越巡査は、西郷優花さんから証拠として預かったSDメモリーカードを紛失してしまったそうなんです。それも、その日のうちに」
証拠品の紛失は、あってはならないミスだ。しかし稀に起こりえるミスでもある。指の先に乗るほどの記憶媒体であるSDメモリーカードは、多くの事件できわめて重要な証拠品として扱われる一方で、紛失のリスクが高い。
「あいつはそのミスを隠すために、西郷さんを殺したっていうんですか?」
「結果的にはそうなったようです」
菰田は能面のような無表情で言った。年齢不詳のこの男は、県警の監察官。警察官の不祥事を取り締まる言わば「警察の警察」である。
先週、この会議室で犯行を自白した水越は、現在、かつて彼が配属を願っていた県警捜査一課の刑事たちから取り調べを受けている。私は五日間の自宅待機を命じられたのち、署に呼ばれ、監察官からの聴取を受けることになった。待機中は情報をシャットアウトされた。関与を疑われているわけではないのだろうが、直属の上司であり責任ありと見られているのだろう。
菰田は続ける。
「預かったはずのSDメモリーカードがどこを探しても見つからないと焦った水越巡査は、三月九日の夜、西郷さんに電話して、被害届を取り下げるよう頼んだそうです。自分のミスをうやむやにするために」
クラブ『ジュピター』の同僚が証言していた西郷優花の電話の相手は、水越だったのか。
西郷優花は取り下げを拒否したという。当然だ。彼女はわざわざ尾崎洋司を怒らせて証拠となる音声を手に入れたのだ。そうまでして受理させた被害届をすぐに取り下げろなどとは、到底、受け入れられないだろう。
水越は直接、西郷優花の住まいを訪れ、説得しようとしたという。
「西郷さんは夜中に自宅に訪れてまで被害届を取り下げさせようとする水越巡査を不審に思い、署に抗議すると言ったそうです。水越巡査としては、そんなことになれば、更に問題が大きくなる。そして、もうこうなったら、西郷さんを──」
殺すしかない。そう考えて、水越は西郷優花を手にかけた。首を絞めて殺してしまった。揉み合った拍子に西郷優花は怪我をして血を流した。拭き取ったつもりだったが、巾木の隙間にわずかに残っていたようだ。
水越は死体を千間沢に埋め、ちょうど当直だった翌日の三月十日、西郷優花が被害届を取り下げたことにした。怪しまれないように、柿沢に電話して取り下げに応じていいか判断を仰いだ。これは賭けだったが、柿沢ならまず間違いなく応じろと判断すると思ったという。
ミスを隠そうとしてより悪い事態を招いてゆく、愚かさの雪だるまのようだ。
「なお、水越巡査が紛失したSDメモリーカードは、署内で発見されました。廊下のタイルの隙間に挟まっていたようです。気づかないうちに落としてしまったのでしょう。水越巡査は署内はくまなく探したつもりだったようですが、見つけられなかったみたいです」
つい、ため息が漏れる。
「あいつ、なんで、そんな馬鹿なことを……」
「わかりませんか?」
菰田はこちらをまっすぐに見て問うた。彼は、私と対峙してからほとんど表情を動かしていない。ポーカーフェイスを保てることは、警察官にとって重要な資質だが、監察官になる者なら尚更だろう。
「もちろん、ミスをしたとき、それを隠したくなる心理はわかります。証拠品をなくしたとなれば、なんらかの処分を受けることは確実です。しかし勇気を持って、相談して欲しかった。結果論ですが、今回のケースはみんなで署内を探せば見つかったかもしれない。大きな不祥事にならないで済んだかもしれないのに」
そもそも、ミスを隠そうと考えること自体が、不適切なのだ。しかも相談に来た市民に被害届けを取り下げさせようとし、あまつさえ殺してしまうだなんて。切羽詰まったとはいえ、水越がそんなことをする人間だったとは、未だに信じられない。いや、信じたくないのか。
「上司として責任は感じています。しかし私なりに職務に誠実であれと伝えてきたつもりです。正直、裏切られたという気持ちも強くあります」
私は本心を口にした。警察がピラミッド型の組織である以上、部下が不祥事を起こしたとき上司も責任を問われるのは、仕方ない。しかし私に何か非があるわけでもない。その無念くらいは言葉にしてもいいだろう。
「なるほど」
菰田はポーカーフェイスのまま頷き、数秒沈黙したあと口を開いた。
「水越巡査はなぜ紛失したことを正直に言わなかったんだと思いますか?」
「それは……何らかの処分を受けると思ったから、じゃないのですか」
私はなぜ改めてそんなことを訊かれるのか、よくわからなかった。
「実は私も昨日、水越巡査本人への聴取を行ったのですが、彼は怖かったからだと言っていました」
「そうですか。処分を恐れる気持ちは、私にもわかりますが……」
「いえ、あなたが、です」
「え?」
私が? 私の何が怖いというのか。
「水越巡査は、あなたにミスを怒られるのが怖かったから、なかったことにしたかったと証言しました」
なんだ、そりゃ?
ついあきれてしまった。
「怒られるのが怖いって、そんな、子どもじゃないんだから」
「精神的に強い負荷を与えられるような怒られ方を何度もしていれば、大人でも、たとえ訓練を受けた警察官であっても、強い恐怖を感じるのではないでしょうか」
菰田はやはりポーカーフェイスのまま言った。
「私が、そういう怒り方をしていると?」
「していないんですか?」
言いがかりをつけられている気分になってきた。
「そりゃあ、それなりに厳しくはしています。警察の仕事は基本的には失敗が赦されないものですから。ドンマイでは済まない。そういうもんでしょう」
「たしかに警察の業務は一般企業よりシビアな面があるのかもしれない。治安組織である以上、上下関係も厳しいものがあるでしょう。しかし、当然ながら、何でもありではない。佐原警部補、あなたは、水越巡査を始めとする部下たちに、度を超して厳しい指導を行っていませんか。あなたのやっていることはパワハラだと、指摘する声もあります」
パワハラ、という言葉で思い当たった。そうか、そういうことか。
「もしかしてそれ、柿沼さんが言ってるんですか?」
菰田は答えないが、私は肯定と受け取った。
「あの人は、自分のだらしなさを棚に上げて、私が注意するとすぐそういうことを言うんですよ。パワハラだとかなんとか。でもね、私はそんなことはしません」
「柿沼巡査部長ではありません」
「は?」
「むしろ柿沼巡査部長は、あなたより年上のため部下の中で唯一パワハラを受けていないと聞きました」
「どういうことです? それじゃあ、まるで私が柿沼さん以外にはパワハラをしているみたいじゃないですか。とんでもない。しませんよ」
「漢字ドリル」
菰田がぽつりと発した場違いな単語に戸惑った。
「え、何です?」
「漢字ドリルです。調書に誤字があった部下を呼び出し、宿直室で徹夜で漢字ドリルをやらせたことがありますか?」
ああ、そのことか。なぜ、今出てくるのかわからないが、私は頷いた。
「ええ、まあ、あります」
「あなたは部下を指導するときは必ず床に正座をさせ、『ゴミ屑』『死ね』などの人格を否定するような言葉をよく使い、ときに部下自身に『私は役立たずのゴミ警官です』と言わせていますね」
「そういうこともありますが……」
そんなの部下を鍛えるためには当たり前の厳しさじゃないか。俺は今、何を訊かれているんだ?
「柿沼巡査部長以外の部下全員に、県警捜査一課への配属を目標とすることを強要していますね」
「いえ、強要なんてしていません」
「しかし、部下が他の目標を口にすると、あなたは『それでは駄目だ』と否定するのではないですか」
「否定なんてしませんよ。ただ、刑事なら捜一への配属は誰もが望むことでしょう。妙な遠慮はいらないと言ってやっているだけです」
菰田は何か考えるように目を伏せてから再びこちらを見た。
「今確認したような行為が、パワハラに当たるという認識はありますか?」
「はあ?」
思わず大きな声が出た。この男は何を言っているんだ?
「いや、どこがパワハラなんですか。若い頃、上司や先輩からさんざんぶん殴られた経験があるからこそ、自分の下の者にはそういうことは絶対しないと決めているんです」
菰田は、表情を変えないまま、目をしばたたかせる。
「もしかして、暴力を振るわなければパワハラではないと思っていますか」
「まさか。たしかパワーは権力で、ハラスメントは嫌がらせのことですよね。暴力を用いなくても立場を笠に着た嫌がらせをすればパワハラになると、そのくらい、わかっていますよ。私はあくまで部下を鍛えるために適切な指導を行っているだけです」
「なるほど」
菰田は一度頷き、数秒の沈黙ののち、言った。
「はっきり言いますが、まったく適切とは思えません。申し訳ないですが、あなたの認知は歪んでいるようだ。あなたが部下にしていることは、立派なパワハラです。今回の不祥事は、それによって水越巡査が追い詰められ引き起こした側面もあると、私は考えています」
キツネにつままれる、とはこのことだろう。馬鹿馬鹿しい。そんなわけないじゃないか。
が、すぐにわかった。
ああ、そうか。この男は、妻と同じ誤解をしているのか。
正義が事故で死んだとき、妻は心労でおかしくなったのか、「あの子はあなたが追い詰めたから自殺した!」などと私を責めた。わざわざ私への恨み言を書いた遺書を捏造までして。遺書は部屋に残されていた。正義の筆跡だと妻は言うが、そんなはずはない。正義が私を恨み自殺するなどあり得ない。正義は私を尊敬してくれていたのだから。
正義は自発的に、私と同じ警察官になりたいと言い出し、そのために大学は法学部を受験し、体力作りのために登山を始めた。妻は私が押しつけたなどと言っていたが、そんなことはしていない。すべて、正義が自分の口で「そうします」と言ったことだ。私は父親としてあいつの手伝いをしてやっていただけだ。もちろん、適切に叱ったことは何度もあるが、追い詰めてなどいない。
あれは事故だった。正義が自殺したというのは、妻の妄想だ。
菰田もあのときの妻と同じく、警察官の殺人という大不祥事を前に、心労で混乱しているに違いない。ポーカーフェイスに見えるが、認知が歪んでいるのはこの男の方だ。
しかし菰田は曲がりなりにも県警の監察官。家のことしか知らない妻とは違う。きちんと説明すれば、わかってくれるはずだ。なあ、そうだよな、わかってくれるよな。
私は敢えて満面に笑みを浮かべ、力強く言った。
「それは誤解なんですよ。わかってもらえるまで説明します。どれだけ時間がかかってもね」
なぜだろう。ずっとポーカーフェイスを保っていた菰田の顔が引きつったように見えた。
(了)
■警察小説競作
月村了衛「ありふれた災厄」
深町秋生「破断屋」
鳴神響一「鬼火」
吉川英梨「罪は光に手を伸ばす」

