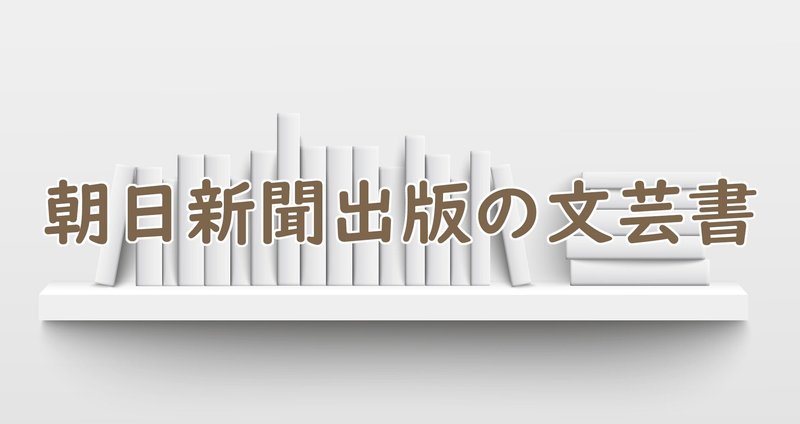#文庫解説

多くの苦しむ女性に支持されたあのロングセラーが待望の文庫化!『母が重くてたまらない 墓守娘の嘆き』三宅香帆氏による解説を特別掲載!
信田さよ子の達成とは何だったのか。母娘問題やDVやアディクション(嗜癖)問題を扱う臨床心理士の第一人者であり、日本一本を精力的に出版している日本公認心理師協会の会長であり、さらにいまもカウンセラーとして臨床の場に立ち続けている。そういった達成は知られている。もちろん私も知っている。それでもなお、言いたい。信田さよ子の達成とは、日本の母娘問題に「夫」の姿を引っ張り出したことである。私はそう考えている。 本書は春秋社から2008年に刊行された。臨床心理士の信田さんが、カウン

\これぞ伊坂幸太郎の集大成/「そうだ、こういうのが読みたかったんだ、と思った。」/大矢博子さんによる『ペッパーズ・ゴースト』文庫解説を特別公開!
※解説は本作のストーリー展開に少々触れている箇所がございます。ご注意下さい。 2020年に新型コロナウィルスが世界を襲ってからというもの、最初の半年は混乱の中に放り込まれ、次の1年は次々更新される情報と新しい生活様式になんとかついていこうと頑張り、そして2021年の秋には、私たちはすっかり疲れ果てていた。 そんな時に刊行されたのが本書『ペッパーズ・ゴースト』である。 飛沫感染で未来が見える超能力……? それまでの人生でほとんど使ったことがなかった「飛沫感染」と

【いまこそ読みたい!不朽の名作】吉川英治文学賞受賞の傑作短編集、待望の復刊/北原亞以子著『夜の明けるまで 深川澪通り木戸番小屋』末國善己さんによる文庫解説を公開
江戸の市中には、警備を容易にするため町の境界に木戸があった。木戸は夜四つ(午後10時頃)に閉じられ、それ以降に木戸を抜けるには、(町医者と産婆を除いて)木戸番がチェックをした後に、木戸の横に作られた潜戸を通っていたという。 犯罪が起こると、木戸を閉じて捕物に協力する木戸番は、町を火事と犯罪から守っていたが、少ない予算で運営されていたため、屈強な若者ではなく安い給料で働いてくれる老夫婦が雇われることが多かった。給料が少ない代わりに、木戸番は番小屋での商売が認められていて、

人を殺める道具であるはずの刀に魅いられる心理を細やかに描き分ける/山本兼一著『黄金の太刀』清原康正氏による解説を特別掲載!
山本兼一は日本刀が持つ魅力を物語の中で存分に表現し得る作家である。江戸時代前期の刀鍛冶・虎徹の情熱と創意工夫、波瀾と葛藤のさまをたどった長編『いっしん虎徹』、幕末期に四谷正宗と称賛された名刀工「山浦環正行 源清麿」の鍛刀に魅せられた生涯を描き上げた長編『おれは清麿』、幕末期の京都で道具屋を営む若夫婦の京商人としての心意気を描いた連作シリーズ「とびきり屋見立て帖」の『千両花嫁』などには、日本刀に関する情報が満載されており、熱い鉄を打つ鎚の音、燃え上がる炎、飛び散る火花の強さな

「仏教文学の新しいジャンルを切り拓いてきたと言ってもいい」伊藤比呂美さん話題の単行本がついに文庫化!/『いつか死ぬ、それまで生きる わたしのお経』曹洞宗僧侶・藤田一照さんによる文庫解説を公開
伊藤比呂美さんは、「ひろみ」と呼ばれると快感を感じると言う。だから、僕は彼女のことをいつも「比呂美さん」と呼ぶことにしている。僕と比呂美さんは二〇一四年八月一日の夜、名古屋市内のとある居酒屋で初めて顔を合わせた。僕が一九五四年生まれ、彼女が一九五五年生まれだから、その年、僕は還暦を迎え、彼女は還暦一年前というタイミングだったことになる。お互いいい歳になってからの邂逅だ。もっとも僕の方は、東京大学の駒場の学生だった頃から彼女の存在を知っていた。身体や性、セックスをテーマに過激

映画に格助詞「と」を持ちこんだ人/暗黒綺想家・後藤護氏による、町山智浩著『ブレードランナーの未来世紀』文庫版解説を特別公開
映画に格助詞「と」を持ちこんだ人 ――スペシャリストにしてジェネラリストであること 『ブレードランナーの未来世紀』というタイトルとは裏腹にクローネンバーグの『ビデオドローム』論からはじまる、という構成が本書の妙ではあるまいか。つまりこの第一章で、『ビデオドローム』が依拠したとされるマーシャル・マクルーハンの思想が語られている箇所が私には重要に思えてならないのだ。本書で語られたその概要をおさらいすると以下のようになる。中世のヨーロッパ人や非文字文化のアフリカ部族などが属して

「認知症の人をどこまで治療すればいいのか」読者に突きつけ続ける難題…現役医師による医療サスペンスの傑作『生かさず、殺さず』/日髙明氏による解説を特別掲載!
「認知症小説」で、タイトルが『生かさず、殺さず』。なんだか不穏だが、読み終わると、たしかにこの小説は「生かさず、殺さず」の物語だと思える。 久坂部羊さんには本作のほかに、認知症をテーマとした作品がある。『老乱』(2016年)は、認知症が進行していく戸惑いや怒りを本人とその家族という二つの視点で活写していた。『老父よ、帰れ』(2019年)は、認知症になった父親を自宅で介護する家族の苦労や近隣との摩擦を描いていた。 本人、家族、地域の人々の立場で認知症を扱ったこれらの作品